令和3年度岐阜県森林研究所研究成果発表会を開催しました。
令和3年7月16日に、令和3年度岐阜県森林研究所研究成果発表会をオンラインセミナー形式で開催しました。森林・林業関係者を中心に、87名の方々の参加がありました。 オンライン形式による開催は今回が初めてで、例年と比べ、県外の方からの参加が多くなりました。
当日の口頭発表は、シカ被害対策、ヒノキの病害対策、トリュフの栽培技術、森林路網の災害リスク評価、木材の人工乾燥技術の5課題で、川上から川下までを繋ぐ話題を提供しました。各課題に対し、数多くの質問が寄せられ、大変盛況な発表会となりました。発表会のアンケートの結果でも、好評でした。 また今年度のポスター形式の資料発表は、森林研究所ホームページ上へ資料を掲載し、質問等を募集しました。
今後も発表会の際にいただいた意見を参考に、岐阜県の森林・林業に貢献する研究技術開発を行っていきます。
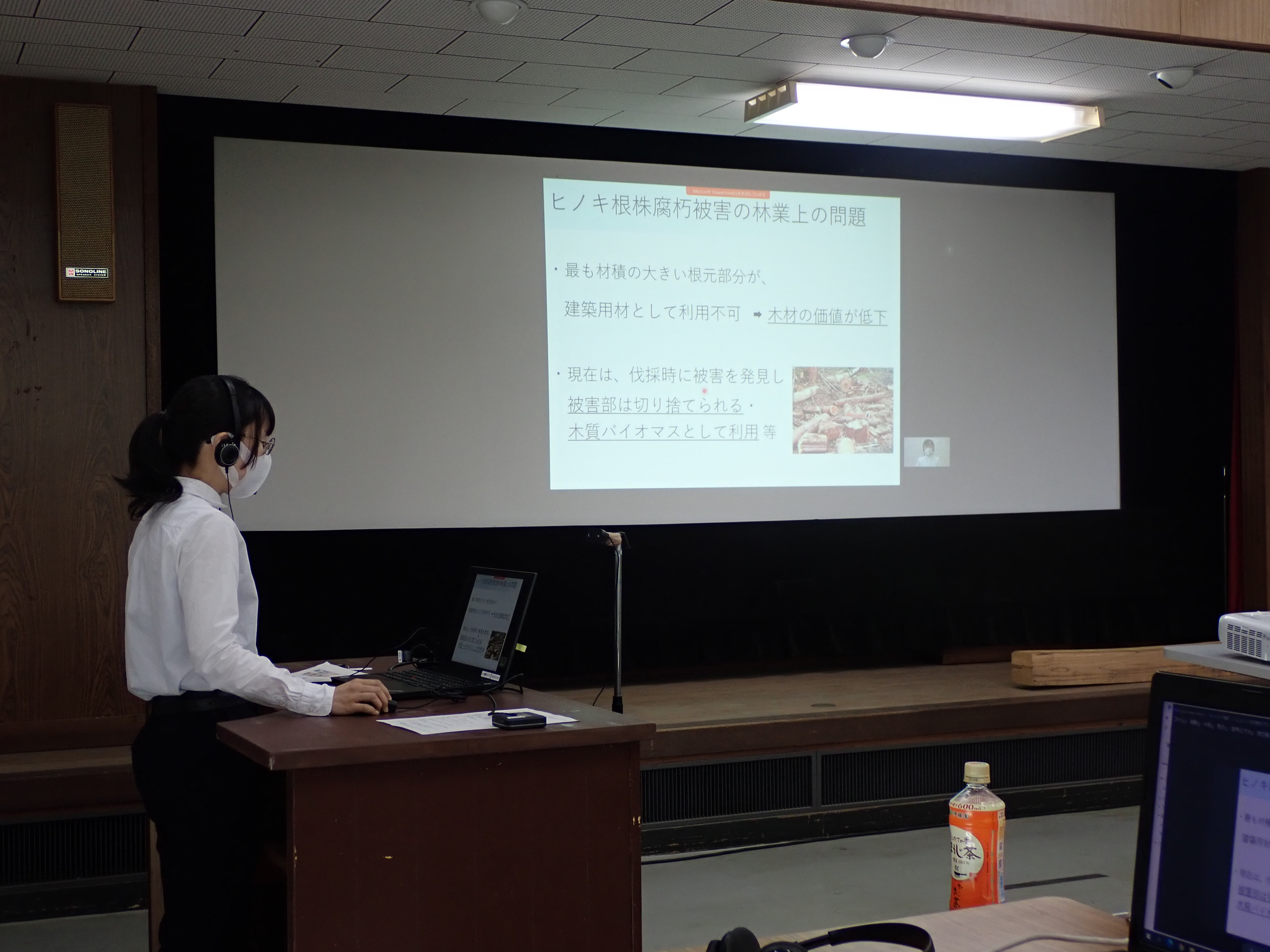
|

|
| 当所研究員発表の様子1 | 当所研究員発表の様子2 |
森林文化アカデミーの学生に、「山地災害リスクを考慮した木材生産」の講義を行いました。
令和3年6月7日(月)に、岐阜県立森林文化アカデミーのクリエーター科2年生4名を対象に講義を行いました。
最初に、日本および岐阜県における山地災害の起こりやすさと、山地災害リスクを考えるうえで重要となる保全対象との距離などについて、室内講義を行いました。
その後、崩壊危険地形を判別するのに役立つ現地指標として、立木の曲がりや地盤の湿潤指標などについてアカデミー演習林付近の林道・森林作業道を歩きながら解説しました。
現地では、地形の特徴を把握するのに役立つ地図としてCS立体図や傾斜区分図などをタブレット上に表示して、それらの地図情報と現地指標を同時に見ることで、「鳥の目線」〜「アリの目線」までを使って、地形の特徴を把握するコツを実感してもらいました。
講義を受けた学生からは、現地で様々な質問があり、関心の高さを感じました。今後は今回学んだ知識を活かして現場を見ていただき、崩れにくい森林づくりに貢献していただきたいと思います。

|

|
| ソーシャルディスタンスに配慮した室内講義 | 崩壊跡地において地盤の湿潤指標などを解説 |
令和2年度6月補正予算を用いて、新規試験機器等を整備しました。
当研究所では、新型コロナウイルスの感染拡大の終息後を見据え、新たな製品開発や品質向上に取り組む林産事業者への支援体制の強化や研究開発のスピードアップを図るため、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を活用し、新規試験機器等を整備しました。
主な機器は恒温恒湿室、自動4面かんな盤、GC-MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)です。
恒温恒湿室は、装置内の温度、湿度を一定に調整することや、プログラムによって温度、湿度を経時的に変化させることができる装置です。
当機器は開放利用ができるよう準備を進めており、製材品やフローリング等の木製品の寸法安定性評価や、耐腐朽性の評価など、幅広い試験依頼に対応することが可能です。開放利用の体制が整いましたら改めてお知らせします。
自動4面かんな盤は、一度に4面を切削し、目標の寸法にする装置です。今までは一度に1面のみを切削しており、なおかつ一度の切削量が1mm程度と非常に小さく、加工に時間がかかっている状況でしたが、短時間で多くの試験材を加工できるようになり、作業効率が大幅に改善しました。
GC-MS(ガスクロマトグラフ質量分析計)は、シイタケ等のキノコ類に含まれる揮発性有機化合物などの複合成分を成分ごとに分離して各成分の定性・定量分析が行える機器です。これにより、キノコの味覚や香りを含む各種成分を素早く解析・数値化することができ、時間経過による品質変動の計測も容易になりました。
これらの新規機器を活用し、県内企業の製品・技術開発支援に努めてまいります。
|
|
|
|
| 恒温恒湿室 | 自動4面かんな盤 | GC-MS |
| (ガスクロマトグラフ質量分析計) |