ヒノキ人工林の表土流亡を防ぐために
−研究成果をまとめた冊子を作成しました−
(岐阜県森林研究所)渡邉仁志
森林のたより 2006年6月号掲載
 |
■はじめに
ヒノキ人工林は、間伐がきちんと行われないと、林冠が閉鎖し、林内が暗くなるため下層植生が衰退しやすくなります。下層植生がない林は、見通しがいいし作業がしやすいので、ともすると歓迎されることもあるようです。しかし、このような林では、地力の低下や河川への土砂流出を引き起こす、表土流亡が発生します。ヒノキ林における下層植生の衰退と表土流亡の問題は、たびたび指摘されていますが、いまだ有効な解決方法が提示されていないのが現状です。
森林研究所では、下層植生の少ない(表土流亡が著しい)ヒノキ林を下層植生の繁茂した(表土流亡の少ない)林へと誘導する方法を検討しています。その成果の中から、ヒノキ林の管理上、表土流亡について知っておいていただきたいことを冊子にまとめました。
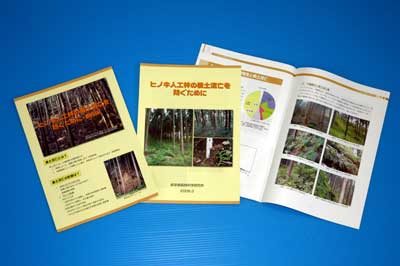 |
冊子(17ページ)は、
- 表土流亡とは何か
- ヒノキ人工林の下層植生と表土流亡
- 表土流亡を防ぐ工夫
- 今後の課題
で構成されています。現場で使っていただくことを目的に、表土流亡という現象について、データや写真をふんだんに用いて解説しました。また、冊子の内容をより簡潔にまとめた要約版(4ページ)も作りました。以下は、冊子のダイジェストです。
■こんな林分では表土流亡が起きています
表土流亡が発生しているかどうかは、下層植生の種類と量、斜面の傾斜、地表面の状態に注目して林をチェックします。ある程度傾斜があり、地表面に下層植生や落葉落枝が少ない林(写真)では、表土流亡が発生していると考えてよいでしょう。
■表土流亡を防ぐ工夫
下層植生が衰退した林は、表土に種子がほとんど含まれていないことから、通常の間伐だけで下層植生を回復させることは困難です(本誌621号)。ですから、下層植生が衰退しつつある林では、植生があるうちに早めの間伐を行うことが大切です。既に下層植生が衰退して、表土流亡がみられる林においては、間伐木を等高線方向に並べたり、払った枝葉を地表面に散布すると、表土流亡を防ぐ効果があります(本誌625号)。
■おわりに
この冊子で示すことができた工夫は、表土流亡を防ぐための対症療法でしかありません。当研究所では、今後も試験・研究を継続し、下層植生を発達させるための間伐方法(表土流亡の根本的な解決方法)を検討していきます。強度間伐がよいのか、列状間伐がよいのか、一部を群状に伐ればよいのか、これから明らかにしなければならないことはたくさんあります。
そこで、そのための試験地を探しています。通常の間伐に加えて、群状間伐の実施が可能なヒノキ林がありましたら、ぜひ私たちの試験にご協力ください。
この冊子を配布しています。希望される方はお問い合わせください。