ヒノキ人工林の下層植生
−間伐で発達するとは限らない−
(岐阜県森林科学研究所)横井秀一
森林のたより 2005年6月号掲載
【間伐しても草が生えない?】
本誌(岐阜県の林業)の昨年12月号に、「間伐しても下層植生が発達しないヒノキ林があり、表土に含まれる埋土種子の少ないことがその理由の一つである」と書きました。そのときは、埋土種子の話がメインであったため、間伐と下層植生の発達の関係については、詳しく触れませんでした。
話が前後になりますが、今回は、ヒノキ林の間伐と下層植生の関係について、研究所での調査結果を紹介します。
【間伐したヒノキ林の植生】
この調査は、中濃地域と東濃地域で行いました。対象は、間伐後1〜7年が経過したヒノキ林26林分で、その林齢は20〜37年でした。
下層植生は、地上高0〜0.3mと0.3〜2mの、2つの層に分けて調査しました。図は、2層の植被率の合計が大きい順に、調査地を並べたものです。植被率の合計が100%を超える林からほとんど0%の林まで、調査したヒノキ林の下層植生の植被率は、様々でした。間伐後に下層植生が発達している林もあれば、発達していない林もあることがわかりました。
こうした違いは、何が原因しているのでしょう。植被率の合計と断面積間伐率の相関はプラス、同じく調査時のヒノキの密度や材積、収量比数との相関はマイナスでした。ただ、その関係は、統計学的に意味があるほど強いものではありませんでした。このことは、間伐は下層植生の発達にプラスの影響を及ぼしているが、植生の発達程度は間伐だけでは説明できないことを示しています。
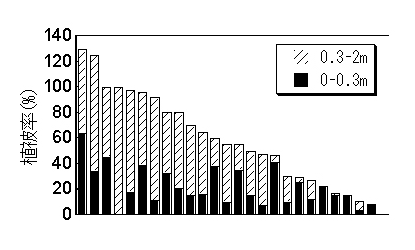 |
【間伐時の植生の存在が重要】
植被率の合計が大きい林の下層植生は、ミヤコザサやスズタケなどのササ類、ウラジロやコシダ、あるいは低木でした。これらは、生育状況からみて、間伐後に急激に発達したわけではなさそうです。間伐前から存在した植生が、間伐による光環境の改善で、いっそう元気に繁茂した可能性が高いと考えられました。これらは、適切に間伐が行われ、下層植生が衰退することがなかった林でしょう。
一方、植被率合計が小さい林は、間伐前からの植生がほとんどなく、新たに芽生えた植物もわずかでした。間伐前からの植生が少ないのは、林冠がうっ閉して林内が暗い期間が長く、その間に下層植生が衰退したためだと考えられます。新たに発生した植物が少ないのは、表土に含まれる埋土種子が少ない(本誌615号)ことが影響していると考えられます。また、間伐による光環境の改善の程度が、種子が発芽して、芽ばえが定着するのに不十分だった可能性もあります。
今回の結果は、下層植生が衰退したヒノキ林(こういう林こそ緊急に植生を回復させたい)は、通常の間伐で下層植生を回復させることが困難なことを示しています。前回の繰り返しになりますが、ヒノキ林では下層植生が衰退する前の間伐が大切です。
 ミヤコザサが繁茂するヒノキ人工林(間伐後1年) |
 低木が繁茂するヒノキ人工林(間伐後4年) |
 芽ばえがほとんどないヒノキ人工林(間伐後5年) |