ヒノキ人工林と表土流出(2)
−表土流出防止から間伐を考える−
(岐阜県森林科学研究所)井川原弘一
森林のたより 2005年10月号掲載
 |
先月号では、ヒノキ人工林はスギ林などに比べて表土の移動量が多いこと、林床植生の少ないヒノキ林では表土の移動量が多いこと、表土の移動防止には地表面に近い層の植生が効くことについてお話ししました。今月は、林床植生が乏しいヒノキ人工林における表土流出防止を考えた間伐方法について検討します。
【県内のヒノキ人工林】
岐阜県内の民有人工林面積のうち57%はヒノキ人工林です。全国平均が26%であることを考えると、岐阜県はヒノキ人工林の割合が高いことがわかります。また、間伐の必要な3〜9齢級は、ヒノキ人工林の73%(130千ha)と非常に大きな割合を占めています。先月号でお話ししたように、ヒノキ林では手入れが遅れると林地保全上、大きな問題が発生します。
そのため、ヒノキ林の適正な管理は県土の保全上、重要な課題となります。
【間伐すれば林床植生は発達するのか】
間伐の履歴がわかる26林分について調べた結果、林床植生の乏しい林分では、間伐しても植生は、ほとんど発達していないことがわかりました。
間伐は、林床の光環境を改善するなど林床植生の発達に対してプラスの影響を及ぼします。しかし、植生が発達するには、間伐以外にも大きな要因があるようです。「詳しくは、本誌621号(2005年6月)を参考に」
【なぜ発達しなかったのか】
林床植生の乏しいヒノキ林を間伐しても、植生が発達しなかった原因は何でしょうか。それは、林床植生の乏しいヒノキ林では、発芽可能な種子が表土とともに流出しているため、種子の量が極端に少なかったためと考えられました。「詳しくは、本誌615号(2004年12月)を参考に」
このことから、林床植生の乏しいヒノキ林において植生を発達させるためには、まず、発芽可能な種子の流出を止める(表土の移動を止める)こと、そして、種子が発芽し、生育していくのに十分な光環境を確保することが重要であると考えられます。
【表土流出を防ぐための工夫】
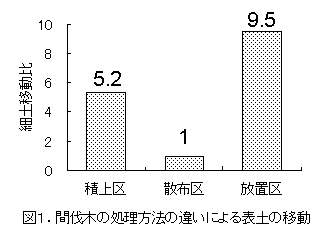 |
そこで、間伐作業時に表土の移動を抑える工夫ができないか検討しました。林床植生の乏しいヒノキ人工林を本数率で3割間伐し、間伐木の処理方法を違えた試験区を設けて、表土の移動量を測定しました。
「積上区」では伐倒木の樹幹から枝葉を払い、樹幹を玉切った後、枝葉とあわせて林地内に積上げました。「散布区」では伐倒木の樹幹から枝葉を払い、樹幹は長いまま等高線方向に接地させ、地表面には枝葉を散布しました。「放置区」では伐倒木をそのまま放置しました。
その結果、1年間に移動した細土の量は、散布区が最も少なく、放置区のおよそ10分の1でした(図1)。ほかの研究事例などとあわせて考えて、伐倒木を地面に接地させることが、表土移動の抑止に貢献すると考えられます。
【今後の課題】
間伐後3年が経過したこの林分においても林床植生は、ほとんど増えていません。この理由として、
- 林床の発芽可能な種子はすでに流出し、量が少なかったこと、
- 新たな種子の供給が少なかったこと、
- 従来行われてきた間伐では、林床の光環境を改善するまでの効果がなかったこと
などが考えられます。
現在は、林床植生の発達のための間伐方法について検討しています。