シデコブシを絶滅から守るために
(岐阜県森林科学研究所)中島美幸
岐阜県の林業 2002年4月号掲載
○春を告げる木 ―「シデコブシ」
「シデコブシ」は、平成13年4月号の「岐阜県の林業」でも紹介したように、東濃地域を中心に分布するモクレン科の植物です。シデコブシの花は、直径が6〜11センチと桜に比べるとずっと大きく、花弁数は9〜30枚以上と変異に富んでいます。花の色も白や淡いピンク、濃いピンクから赤紫色と様々です(写真―1)。また、桜と同様に、開葉に先立って花が咲くため、白やピンク色の大きな花をいっぱいに付けた姿は、まさに春一色といった感じで大変美しいものです。
しかし、自然のシデコブシが春を告げる場所は、とても限られています。それどころか、近年はその場所さえも失われつつあるのです。
そこで今回は、遺伝的多様性の保護の点から、シデコブシの保全に向けた提言をしたいと思います。
 |
○シデコブシの分布域
シデコブシは、愛知県の渥美半島、豊田・瀬戸付近、岐阜県東濃地域と中濃地域、そして三重県四日市市付近の伊勢湾を取り囲む丘陵地の湿地やその周辺にのみ分布しています。また、地域によってシデコブシの分布の仕方は異なっています。近年、宅地造成やゴルフ場開発、道路建設などの開発行為による自生地の消失や分断化が急速に進んでおり、レッドデータブックでは「絶滅危惧II類」に分類されています。
○地域ごとのシデコブシ自生地
それでは、シデコブシ自生地について地域ごとに紹介していきましょう。
- 愛知と三重:ここのシデコブシ自生地は、岐阜県から遠く離れたところに位置しています。また、岐阜県と比べると集団数が少なく、分布が非常に限られているのが特徴です。
- 岐阜県関市・各務原市:この地域には、市街地や水田、道路などによって分断されたシデコブシ自生地が多く存在します。また、集団あたりの個体数が少ないのが特徴です。道路建設予定地となっており、消滅する運命にある集団や、他の樹種に被圧されて衰弱している個体が多い集団もあります。
- 岐阜県東濃地域:東濃地域には多くのシデコブシ自生地が連続的に分布しており、最大級の分布域を誇っています。自生地のおかれている現状は、天然記念物に指定され保護下にあるものから、開発予定地となっていて消滅が危惧されているもの、自然状態にあるものまで、大変様々です。また、シデコブシと近縁なタムシバが混在している自生地もあります。さらに、恵那市飯地町の自生地は、シデコブシ分布域の中でも最も標高の高いところに分布しています。距離的には、東濃地域の他の集団と近接していますが、標高的に隔離された集団だといえます。
○シデコブシの遺伝的多様性
シデコブシの分布の仕方は地域ごとで様々であることが分かったと思います。ここでもう一つ、地域ごとのシデコブシの特徴を知る指標として、「遺伝的多様性」というものがあります。遺伝的多様性とは、その集団における遺伝子のバリエーションをいいます。生物の遺伝的多様性を調べることは、保全に向けた基礎資料を集めるためにも重要なことの一つです。
シデコブシの遺伝的多様性を調べるために、岐阜県中濃地域の二集団(関、各務原)、岐阜県東濃地域の五集団(多治見、土岐、瑞浪、恵那、飯地)、愛知県の二集団(田原、豊田)、三重県の一集団(菰野)を対象に、遺伝解析を行いました。
その結果、岐阜県のシデコブシは愛知県や三重県と比較すると高い遺伝的多様性を持っていることが分かりました。また、対立遺伝子の分布パターンは集団によって異なる傾向が見られました(図―1)。特に、東濃地域では集団が互いに近接しているにもかかわらず、それぞれの集団が独自の遺伝的多様性を維持していることがわかりました。
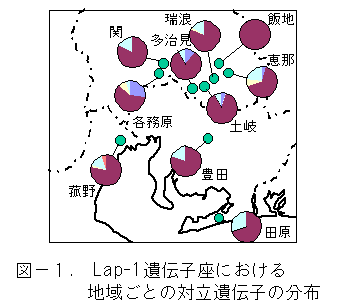 |
○シデコブシの保全に向けた提言
今回の遺伝解析の結果は、岐阜県のシデコブシが非常に多様な遺伝資源の宝庫であることを表しているといえるでしょう。しかし、自生地の消失や分断化によって、集団あたりの個体数が減少すると、遺伝的多様性は低下しやすくなります。また、近親交配によって集団が衰退する恐れも出てきます。シデコブシの遺伝的多様性を保全していくには、集団あたりの個体数を下げないことが重要だと思われます。
また、集団ごとの遺伝的独自性を保つためには、集団間の安易な移植は避けるべきだと考えられます。
東濃地域にはシデコブシの他にも、ハナノキやヒトツバタゴなどの地域固有種が分布しており、世界的にも大変貴重な植生をなしています。その一方で、開発予定地と重なっているために、消滅の運命にある自生地もたくさん存在しています。このような貴重な自然が、開発行為によって失われていくのは非常に残念なことです。
このような貴重な樹木の保全方法について検討するため、森林科学研究所では、平成13年度から「岐阜県の世界的固有種(樹木)の遺伝子解析とクローン増殖に関する研究」と題するプロジェクト研究に取り組んでいます。当研究所のホームページにも掲載していますので、一人でも多くの方にアクセスして頂きたいと思います。
今後もさらに詳しく遺伝解析をすすめていき、シデコブシを絶滅から守るための方法について検討していきたいと思います。
このホームページにご意見のある方はこちらまで