今回は、この白しめじの栽培技術並びに他系統との栽培比較を行いましたのでその結果を報告します。
【白しめじとは】
白しめじはヒラタケの突然変異株の白色系亜種です。特徴としては、傘の色がヒラタケのように黒色ではなく、白色をしています。
当センターでは、平成元年にこのきのこを入手し、組織分離により菌株を得ました。その後、保存菌株(白色1号)として継体培養を行い、現在に至っています。
【菌床栽培への試み】
この菌株を用いて、菌床栽培の可能性について検討しました。
《安価なスギオガ粉の利用》
栽培を行う上で最も重要なのが培地組成です。通常、ヒラタケ栽培では培地基材としてシイタケ栽培等で利用されているブナやコナラなどの広葉樹のオガ粉ではなく、価格の安い針葉樹(スギ)のオガ粉が利用されています。
そこで、この白しめじについても培地基材としてのスギオガ粉の利用を検討しました。
その結果、スギオガ粉の培地だけでも品質の良いきのこが発生することが確認されました(表1)。
| 試験区 | 培地組成(容積比) | 1番発生(g) | 2番発生(g) | 発生量(g) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スギ | ブナ | フスマ | コメヌカ | ||||
| スギ | 10 | -- | 2.5 | 1 | 82 | 32 | 114 |
| スギ・ブナ | 5 | 5 | 2.5 | 1 | 82 | 31 | 113 |
| ブナ | -- | 10 | 2.5 | 1 | 76 | 33 | 109 |
1.スギ間伐材の利用促進
2.資材の入手が容易
3.生産性の向上
等様々な面で利点があるので、この栽培技術の実用性は高いものと思われます。
《培養日数の検討》
栽培工程の中で最も期間を要するのが培養日数です。この培養日数が短縮できれば、工程の簡素化を大幅に図ることが出来ます。
そこで、培養日数ときのこの発生状況を検討したところ、1番発生では培養日数が長いほど収穫するまでの日数は短くなりました。
これは培養が長くなると培地の熟成が増し、移動後早期に子実体が発生したためと思われます。しかし、発生量は37日培養が最も多くなりました。また、2番発生を含めた総発生量も37日培養が最も多く、26日、47日培養の順となりました(図1)。
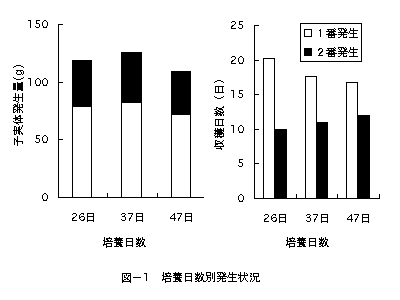
このことから、実用化を進めるには26日と37日の中間日数である32日前後が適当と思われます。
【栽培工程】
白色1号の栽培工程は図2に示すようにヒラタケ栽培とほぼ同じで短期培養が可能です。また、発生も2回見られ、総発生量は100グラム以上が期待できます。
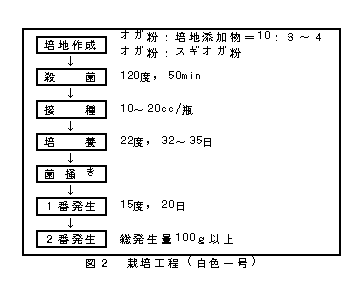
【他系統との比較】
白いヒラタケで購入可能なものに菌興の19号菌があります。
今回はこの系統を用いて栽培比較を行いました。菌興19号の発生状況は38日培養の方が45日培養に比べて良い発生が見られました(図3)。
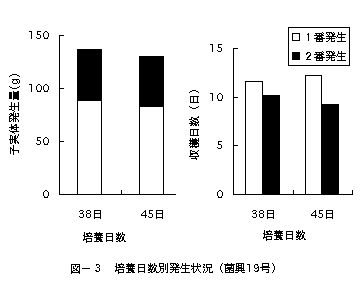
白色1号と比較すると培養日数ではほぼ同様の32〜35日程度です。また、発生量は白色1号の方が若干少なくなりました。
しかし、きのこ自体の堅さは白色一号の方が堅いことから、日持ちが良く、夏期のきのことして利用できるものと思われます。
【おわりに】
白しめじの菌床栽培について検討したところ、ヒラタケ栽培同様安価な材料で短期間に栽培できることが分かりました。また、白色1号も発生状況等から考えると市販品種に劣らない優良な系統であることも分かりました。
今後は、更なる栽培技術の向上を進めつつ、技術指導に力を入れていきたいと考えています。