そこで、菌床栽培においても効果があるのではないかと考え、木炭粉の添加効果について検討したので、その概要について報告する。
・ヌメリスギタケ
1.添加効果(混合割合)
市販の木炭粉(粒度1mm以下)を培地乾重量の5、10、20、30%添加し、添加効果を検討した。
培地はオガ粉に培地添加物(フスマ)を容積比で10対2に混合したものを標準とした。この標準培地に前述のように混合した培地を菌床栽培用の800ccの耐熱性の瓶に詰め、高圧殺菌した。放冷後種菌(林業センター保存野生菌株)を接種し、22℃で36日間培養した。
発生は15℃、85〜95%の条件下で行った。子実体は膜が切れた時点で収穫し、生重量と個数を測定した。
また、発生は2回行った。
試験の結果を図−1に示す。
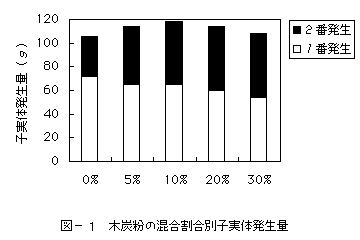
標準の0%区に比べて、木炭粉を添加した培地の方が発生量が多かった。
これは各試験区の2番発生が0%区の平均値34gに比べて、木炭粉添加区では45〜55gと多く発生したことから、総発生量が相対的に多くなったと考えられた。
これは木炭粉には保水性があり、2番発生時に不足しがちな水分を保持することにより、高収量につながったと考えられた。
このことから、木炭粉を添加する効果はあると思われた。
また、混合割合(添加量)については、10%区をピークに混合割合が増すに従って発生量は減少した。
混合割合としては10%程度が最適である。木炭粉10%添加とは栽培瓶1本当たり木炭粉を20g添加したことに相当する。
2.粒度
木炭粉の粒度について市販の1mm以下、2〜5mm、5mm以上の3種類の木炭粉を用いて、標準培地に10%添加した培地を作成し、木炭粉の粒度と添加効果について検討した。
栽培は添加効果試験と同様に行い、培養は34日間とした。
試験の結果を図−2に示す。
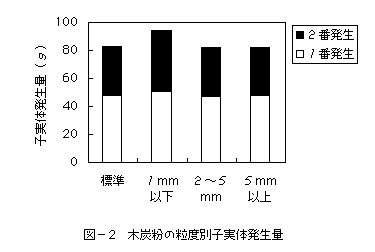
1番発生を見ると各試験区とも顕著な差はなく、木炭粉の効果は見られなかった。
しかし、2番発生では粒度1mm以下の木炭粉添加区で増収が見られ、総発生量では標準区の14%増の発生であった。しかし、それ以外の2mm以上の木炭粉添加区では増収効果は見られず、添加効果は認められなかった。
これは粒度1mm以下の木炭粉がパウダー状であることから、表面積も大きく、培地の隅々まで水分が保持できることから、2番発生に良い影響を与えたと考えられる。
このことから、木炭粉の粒度としては2mm以上の大きさでは効果はなく、1mm程度の粒度が適していることがわかった。
培地組成は次のようである。
| オガ粉 | 145g |
| 培地添加物 | 55g |
| 木炭粉(10%) | 20g |
| 水 | 230g |
| (栽培瓶1本当たりの重量) |
・シイタケ
添加効果(混合割合)
木炭粉(粒度1mm以下)を培地乾重量の3、6%添加し、標準の0%区と比較することで添加効果を検討した。
栽培条件はヌメリスギタケと同様にし、培養は108日間とした。 ただし、オガ粉はブナオガ粉に容積比で20%のドリル屑を加えたものとした。また、種菌は秋山567号菌を用いた。
試験の結果を表−1に示す。発生量を見ると標準の0%区が143g発生しているのに比べ、木炭粉を添加した3%区、6%区とも48〜58g多く発生し、増収効果が認められた。
| 試験区 | 発生状況 | 発生率 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 発生量 | 個数 | 個重* | 1番 | 2番 | 3番 | |
| 0% | 143g | 27個 | 5.3g/個 | 97% | 63% | 56% |
| 3% | 201 | 31 | 6.5 | 100 | 90 | 83 |
| 6% | 191 | 35 | 5.5 | 100 | 83 | 85 |
これはヌメリスギタケ同様、2番、3番発生時に不足しがちな水分を保持することにより、増収につながったと考えられる。
培地組成は次のようである。
| オガ粉 | 270g |
| ドリル屑 | 60g |
| 培地添加物(3%) | 155g |
| 木炭粉(3%) | 15g |
| 水 | 500g |
| (培地1Kg当たりの重量) |
・おわりに
以上のことから、ヌメリスギタケ、シイタケの菌床栽培で木炭粉を添加する効果が認められた。また、ヒラタケでも菌床栽培において、培地に添加することにより菌糸の増殖並びに増収効果があることが報告されている。
ただし、同じヌメリスギタケでも系統によって発生状況に差が見られたことから、系統別に効果を検討する必要があると思われる。
また、今回の試験に用いた木炭粉は広葉樹が主体であることから、今後は針葉樹の木炭粉でも同様の試験を行い、効果について検討していきたいと考えている。
今までは培地のpH調整に添加していた木炭粉も2番発生以降の培地内の水分保持や発生量の増収につながることから一度利用してみてはいかがでしょうか。