菌床シイタケ栽培施設におけるキノコバエ被害
(岐阜県森林科学研究所)井戸好美
森林研情報72号 2003年2月発行
□はじめに
本県の菌床シイタケ栽培は、昭和63年から始まり、飛騨地域や奥美濃地域を中心に順調に生産量を伸ばしてきました。このシイタケは、傘が大きく肉厚で美味であることから、県内外から高い評価を受け、今では「やまっこ」という銘柄のブランド品になっています。ところが近年、このシイタケ生産施設でキノコバエ類が発生し、大きな問題となっています。 キノコバエは、キノコを直接食害する被害を及ぼさないものの、これが付着していると商品価値をなくしてしまいます。しかし、菌床に直接散布できる農薬が登録されていないことや、薬剤の使用はシイタケの健康食材としてのイメージを損ねることから、生産者からは安全性の高い防除技術が求められています。
そこで、岐阜県内の菌床シイタケ生産施設に発生しているキノコバエ類の被害実態を把握するため、アンケート調査を実施し、被害増加の原因について検討しました。
□被害実態の調査方法
アンケートは、岐阜県内の菌床シイタケ生産者を対象に聞き取りや郵送による方法で行いました。
調査項目は、キノコバエの被害と栽培管理方法や施設環境との関係を明らかにするため、発生方法、キノコバエ被害の有無、発生時期、防除対策、生産施設の清掃、廃菌床の処理等としました。
アンケートの回答は、全生産者235人の内116人からいただき、記入漏れ等を除いた113人(48.1%)を有効回答としました。
□キノコバエの発生被害は?
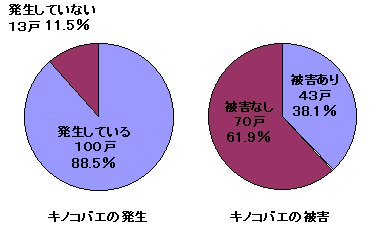 図−1 キノコバエの発生被害 |
キノコバエの発生は図−1のとおり、全生産施設の9割に達し、この内約4割で被害が確認されました。これらの被害は、キノコバエの成虫が包装パック内へ混入するのが大部分を占めていました。また、生産者の多くからは、このキノコバエの混入被害を防ぐため、パック作業にかなり時間を費やしているという意見がありました。
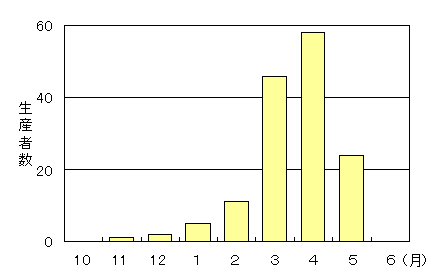 図−2 キノコバエの発生時期 |
また、発生時期は春先の3〜5月に特に多いことが分かりました(図−2)。これは、春先になると気温が上昇するため、キノコバエの生育期間が短くなり、発生回数が多くなるので、増加したと考えられます。しかも、この時期の菌床培地は、キノコの発生が終わりに近づいているため、腐敗が進み、キノコバエの餌になりやすくなることも増加の要因と考えられます。
このため、キノコバエ被害を防ぐには、キノコ収穫が終了した菌床培地は早急に廃棄することが重要だと考えられます。
□どの地域で被害が多いのか?
キノコバエの被害を生産地域別に示したのが図−3です。岐阜県全域では、被害が確認された43戸のうち、郡上地域で2戸確認された以外は全て飛騨地域に集中しました。飛騨地域では、被害が多い地域と少ない地域があることがわかりました。
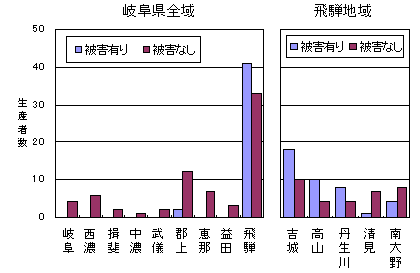 図−3 キノコバエ被害(生産地域別) |
そこで、被害の多い吉城地域と被害の少ない清見地域を比較してみました(表−1)。その結果、清見地域は、栽培管理方法が全面発生の浸水方法であるのに対し、吉城地域は、近年新しい栽培方法として行われている上面発生の施設が多いことがわかりました。しかも、上面発生を行っている生産施設全てでキノコバエの被害が確認されました。
このことから、キノコバエ被害と栽培管理方法の上面発生とに深い関係があると推察されました。
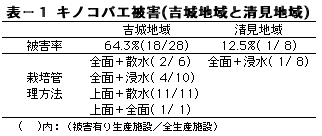 |
□被害増加の原因は?
そこで、キノコバエの被害と栽培管理方法との関係を明らかにするため、栽培管理方法別の被害状況を検討しました(図−4)。その結果、発生方法では全面発生で被害有りが27.6%であるのに対し、上面発生では78.3%で被害の割合が非常に高いことが分かりました。
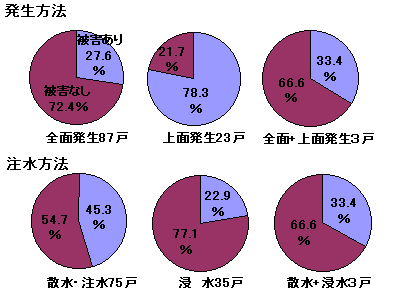 図−4 キノコバエ被害(栽培管理方法別) |
また、注水方法では浸水で被害有りが22.9%と低いのに対し、散水・注水では45.3%と被害の割合が高いこともわかりました。
これは、注水方法が従来行われていた浸水から散水・注水に変わったことにより、培地表面や培地内部のキノコバエ幼虫が水で洗い流されなくなったためと考えられます。
これらのことから、キノコバエの被害増加の原因は、近年増加している上面発生の導入により、注水方法が浸水から散水・注水に変更したためと考えられます。
また、キノコバエの被害と廃菌床処理との関係を明らかにするため、廃菌床処理別の被害状況を検討しました(図−5)。その結果、雑菌の発生した菌床培地をすぐ廃棄した生産者の被害が少ないことがわかりました。このことから、キノコバエ被害を防ぐためには、雑菌の発生した菌床培地はすぐ廃棄することが重要だと考えられます。
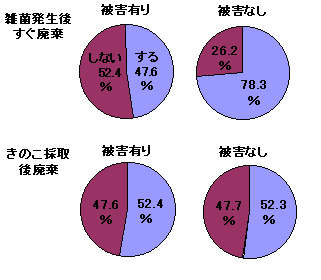 図−5 キノコバエ被害(廃菌床処理別) |
□おわりに
今回の調査から、キノコバエの被害増加は、菌床栽培での注水方法に原因があることがわかってきました。このため、被害を減少させるには以前行っていた浸水に戻すことが有効と考えられます。しかし、一度省力化のために導入した栽培システムを元に戻すことは困難です。
今回のアンケート結果から当所では、上面発生でキノコバエ幼虫を洗い流す効果が得られる栽培技術や化学農薬を使用しない防除技術の開発に取り組む予定です。
このホームページにご意見のある方はこちらまで