サクラの接ぎ木
(岐阜県森林科学研究所)中川 一
森林研情報71号 2002年2月発行
■はじめに
現在「花の都ぎふ」推進の一環として岐阜県内の名桜樹「淡墨桜」、「臥竜桜」、「荘川桜(照蓮寺桜、光輪寺桜)」の4種類について、白鳥林木育種事業地で接ぎ木苗が育てられ、県下に毎年約2,200本が無料配布されています。この育苗については、当所が研究の過程で確立したサクラの接ぎ木方法が生かされています。また、これらの名桜樹はエドヒガン(種名)でありますが、この他にヤマザウラ系の中将姫誓願桜、揖斐二度桜、オオシマザクラ系の太田桜の天然記念物や園芸品種など20種類以上のサクラを接ぎ木して、研究所内に保存・育成しています。
このような経験を基にしてサクラの接ぎ木方法について紹介します。
■接ぎ穂と台木の親和性
主なサクラは、表−1のとおりです。一般に樹木の接ぎ木は、接ぎ穂と台木が同じ種である共台で活着が優れています。しかし、ヤマザクラ群のサクラは、いずれもオオシマザクラを台木として接ぐと良い活着が得られます。また、台木は、挿し木よりも実生苗の方が樹勢が強いためか良い活着となります。
園芸品種のサクラをサトザクラと呼びますが、これらはいろいろな種の性質が混ざり合っていますが大部分はオオシマザウラの性質を強く持っています。従って、これらはオオシマザクラに接ぐと良い活着となり、これらには挿し木で容易に増殖する青肌ザクラと言う台木用品種に接いでも良い活着のものがあります。
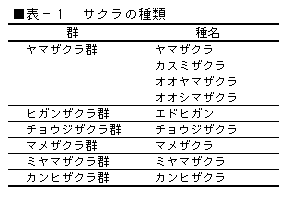 |
■切り接ぎ
- 切り接ぎの時期は、サクラが芽吹く少し前で美濃市では2月下旬〜3月上旬です。
- 接ぎ穂は、芽が堅い1月中旬〜2月上旬に採取します。採取する枝は、葉芽(葉芽は円錐形、花芽は紡錘形)の多い健全で充実した枝です。枝の保存は、乾かないよう切り□をよく湿った布で巻き付け、ビニール袋の中に密閉し、5℃の冷蔵庫に保管します。
- 接ぎ木は、居接ぎでの活着が良く、台木は畑に植栽してある実生苗とします。台木の根元径は、太さ1〜1.5cmで苗齢1〜2年生ぐらいです。
- 接ぎ方は次のとおりです。
- 穂を冷蔵庫からクーラーに移す。(接ぐ直前までクーラーの中に入れておく。)
- 台木は、付着している土などを除去し、地面から高さ約4cmで切断する。
- 充実した葉芽2個と芽の下2〜3cmまでを接ぎ穂とし、枝から剪定鋏で切り取る。
- 接ぎ穂の作製は、台などの上に固定し台木と密着させる部分が平面となるよう、木部が十分表れる幅にナイフで切削する(写真−1)。次に接ぎ穂の基部を約45°で切り戻す。
- 接ぎ穂は、切削部を中にして口にくわえる。
- 台木の接ぎ木部分は、樹皮面に凹凸の無い部分とし、木部、形成層、師部を正確に確認するため木□の一部を斜めにナイフで切削する。
- 台木と接ぎ穂の切削面が平面で密着するように、台木に切れ込みを入れる。幅は接ぎ穂の切削幅より広目に木部まで切り込み、深さは接ぎ穂の切削面の長さより深目とする。
- 台木と接ぎ穂の形成層が少なくとも片側が一致するように、接ぎ穂を台木に挿入する(写真−2)。
- 接ぎテープで接ぎ木部分を巻く(写真−3)。
- 接ぎ穂の芽は出して、土で埋める。
- 出来れば寒冷紗で被覆する。
- 接ぎ木後の管理は次のとおりです。
- 接ぎ穂から新芽が3cm程度伸びたら、旺盛な芽を残して他の芽を剪定鋏で切除する。なお、同程度の勢いであれば下側の芽を残す。
- 台木から直接伸びた芽を全て取り除く。
- 新芽が旺盛に伸び始めたら接ぎテープを切る。
- 切り接ぎの特色は次のとおりです。
- 地際部に接ぎ木できる。
- 接ぎ穂が長期間保存できる。
- 居接ぎよりも活着が劣るが、揚げ接ぎ(畑から苗木を掘取って室内などで接ぐこと)も可能である。
 写真−1 穂の調整 |  写真−2 穂を台木へ挿入 |  写真−3 接ぎテープ巻き |
■芽接ぎ(剥ぎ接ぎ)
- 時期は、枝が固まってきた9月上旬です。
- 接ぎ穂は接ぎ木直前の採穂が良く、親木が近くにあると良い。採取した穂は、切り□を水に浸漬し、クーラーなどで保管します。
- 台木の大きさは切り接ぎと同じです(当年生〜1年生ぐらい)。
- 接ぎ方は、次のとおりです。
- 接ぐのに邪魔な台木の枝、葉、ゴミなどを取り除く。
- 穂の中から接ぐ芽(充実した芽)を決め、その葉身を切除する。
- 芽は上から下に、ナイフで長さ約3cm剥ぐ(写真−4)。この場合、内側に木質部、外側に芽・葉柄を着けて、切削面を平面にする。
- 台木の地際郡に、接ぎ芽よりもやや大き目に平面となるようナイフで切れ込みを入れる。
- 切れ込みの外側上部2/3をナイフで切除する。
- 台木の切れ込みの中に剥いだ芽を挿入する(写真−5)。
- 台木と接ぎ芽の形成層を合わせる。
- 接ぎテープで芽・葉柄を出して巻き込む(写真−6)。
- 接ぎ木後の管理は次のとおりです。
- 翌春、接ぎ木が成功していれば、接ぎ芽を残して台木の芽を除去する。
- 接ぎ芽から伸び出した枝が長くなれば、接ぎ芽の上部の台木を剪定鋏で切除し、伸びた枝は台木からの剥離を防ぐため支柱で支える。
- 芽接ぎの特色は次のとおりです。
- 接ぎ木部位が高くなる。(苗木を定植した場合、台木の枝が伸びやすい。定植は接ぎ木部分は地中に埋める。穂の自根を出させると親和性が悪い場合でもよく成長できる。)
- 出来るだけ台木の近くに接ぎ穂の親木があると良い。
- 切り接ぎより作業効率が良い。
- 切り接ぎよりも活着率が良い。
- 活着したかどうかの判定が早い。(活着しないものは10日程度で葉柄が変色・脱落する。)
- 失敗しても翌年の春には切り接ぎの台木として利用できる。
 写真−4 穂の調整 |  写真−5 穂を台木へ挿入 |  写真−6 接ぎ木終了 |
■接ぎ木のポイント
接ぎ木のための道具は、ナイフ、剪定鋏、接ぎテープ、接ぎ穂調整用台、クーラー、鍬などの簡単な道具で実施可能です。また、サクラは、接ぎ穂と台木の形成層をあまり神経質に合わせなくても比較的良く活着し、慣れればエドヒガンで切り接ぎ60%、芽接ぎ70%程度の活着率が期待できます。
しかし、活看を良くするためには、先ず第一に切れ味の良いナイフが必要です。次いで、実際に接ぎ木を始める時には、穂の調整、台木への切れ込み入れを十分練習してから行うことが必要です。
このホームページにご意見のある方はこちらまで