○ドングリとは
「ドングリ」はブナ科コナラ属などの果実の総称で、「堅果」とか「殻斗果」(かくとか)といいます。これらの特徴は、いずれも種子が「果皮」とよばれる艶のある堅い殻で守られています。これを普段私たちは、ドングリとよんでいます。もう一つの特徴は、ドングリの下部に萼の変化した「殻斗」が着いていることです。殻斗とは一般に「はかま」とか「ぼうし」と呼ばれています(写真1)。ドングリをつける代表的な樹種は、コナラやミズナラです(写真2)。
ドングリとは、種子そのものではなく正確には果実(堅果)を指しますが、ここでは種子という言葉で話を進めます。
 写真1 色々な殻斗 |
 写真2 左ミズナラ 右コナラ |
○成り年 (なりどし)
コナラは、山野に自生しています。このためいつでも種子をつけると思われがちですが、実は2〜3年周期で、豊作や凶作を繰り返しています(図1)。このうち、豊作の年を特に「成り年」と呼んでいます。では、なぜそのような周期ができるのでしょうか。
一つは、種子を生産することにより樹体内の養分を消費するため、その回復を待つためであるといわれています。しかし、この調査は非常に難しいため、連続的に樹木の栄養状態と種子生産の関係について研究された報告はあまりありません。
しかし、同じコナラ属のクヌギに肥料を与えると着花数が増加し、豊作と凶作の差が小さくなったという報告があります。これは樹木の栄養状態が良い状況が続けば、種子が毎年一定レベル以上生産されることを示しています。
同じように、人工的に着花を促進させる方法として、環状剥皮があります。これは、カラマツなどに有効な方法で、幹または枝の周囲を一定の幅で全周または半周ずつ2段に分けて樹皮を剥ぎ取るものです。この処理を行うことにより剥皮より上部で水分、窒素化合物などが減少し、デンプンなど炭水化物が増大します。このことから、樹体内のCとNの比率が、花芽分化に影響を与えていると考えられています。しかし、クヌギではこの方法が必ずしも有効ではないようです。
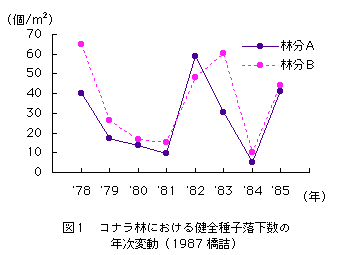 |
○気象の影響
もう一つの原因は、結実に影響を及ぼす気象条件が年によって異なるためだといわれています。一般的に樹木は、高温で乾燥した夏の翌年に、開花・結実が多くなるといわれています。これは、高温や乾燥が花芽の分化を促すためです。
コナラでは、7月から8月にかけてが翌年の花芽の分化時期に当たっています。このため梅雨時から夏にかけて雨の降らない日が多い年は、花芽の分化が促進され、翌年の開花量が多くなると考えられています。
しかし、花がたくさん咲いても雌しべに花粉が着かなければ受精せず、種子は生産されません。特にコナラは風媒花といって風によって花粉が運ばれ受粉するタイプであるため、雨が降ると花粉の飛散量は少なくなります。このため花の咲く時期に雨が多い年は、種子の結実量はあまり多くならないようです。
○豊凶の予測
コナラ種子の豊作・凶作の周期には、前述した原因のほか光環境等も複雑に絡まりあって作用しています。このため気象変動等で周期がずれ、凶作が長く続いたり、逆に2年連続して豊作がくることもあります。
過去の気象や種子生産量のデータを統計的に解析してみても、各年の作柄を説明しきれないことも多く、天気予報と同じようにおおよその周期はわかっていても正確な予想はかなり困難です。
このほか、豊作は一定の地域で同時に発生するといわれています。しかし、どの程度の範囲で豊凶が同調するかといったことが不明なため、現在も各地で調査が行われています。
○終わりに
種子の作柄に豊作・凶作の周期がある話は、コナラに限った事ではありません。その他の樹種についても豊凶はありますが、コナラとは周期、豊作を引き起こす条件は異なっています。
秋に限らず、野外に出たときは天気や花の咲き方、実の付き方などにほんの少し注意を払ってみると、意外な変化に気が付くことがあります。