

樹幹流採取装置と根尾村ブナ林の衰退状況
酸性雨は、様々なメディアで取り上げられ、現在では誰もが知っている環境問題の一つとなっています。調査も市街地を中心に行われ、その結果が公表されています。しかし、森林地域の調査は少なく、全国を同一レベルで行う調査に至っては皆無です。
そこで、当林業センターでも酸性雨対策として、平成2年度より美濃市の降水調査と、林野庁の依託で全国を同一レベルで調査する「酸性雨等森林被害モニタリング事業」を実施しています。今回は平成2〜4年度の調査結果から、岐阜県南部における森林地域の降水と森林の実態について紹介します。
1.酸性雨の樹木への影響
酸性雨の樹木への影響は、葉の組織を破壊する地上部への影響(直接的影響)と、森林土壌の酸性化に伴うカリウムやカルシウム等栄養塩の流出、アルミニウム等有害金属の溶出といった地下部への影響(間接的影響)が報告されています。
2.岐阜県南部における森林地域の降水の状況
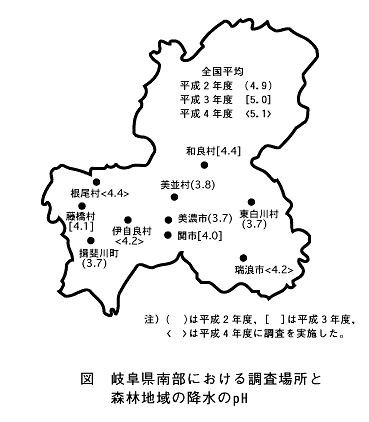
図に岐阜県南部における調査場所と森林地域の降水のpHを示しました。調査は、6月の後半に1回、裸地で10日間採取した降水(林外雨)について行いました。
各調査場所のpHは3.7〜4.4で、同一時期に実施した全国平均の4.9〜5.1、酸性雨の基準である5.6を大きく下回りました。しかし、10日間の降水を1回調査した結果であることから、たまたま低いpHであった可能性もあります。美濃市で継続して3年間調査した結果は、pHの最低3.5、最高5.9、平均4.3でした。また、人工酸性雨を散布する試験で、葉面に可視障害が現れるのはpH3.0以下と報告されていることから、現在程度の酸性雨では直接的影響は考えられません。但し、新聞等で報道されている山岳地域の酸性霧は、pH3.0以下の観測値もあり、その影響が心配されます。
3.岐阜県南部における森林土壌の化学性と森林の状況
日本は蒸発散量より降水量が多いので、土壌中の水は基本的に表層から下層へ移動します。このため、土壌中の塩基が流亡し、土壌は酸性化します。一方、土壌には落葉落枝等が供給され、有機物層を形成し、その分解によって生成される有機酸により酸性土壌になっています。従って、日本の森林に広く分布する褐色森林土、黒色土の鉱質土壌のpH(H2O)は4.5〜5.5の範囲にはいるものが大部分です。低温や乾燥の環境にあり、有機物層の分解が不良なポドゾルのA層、尾根筋の乾性の褐色森林土、赤・黄色土のpHの範囲はそれより低いといわれています。
表に岐阜県南部における表層土壌の化学性を示しました。
| 調査場所 | 林型 | 地質 | 土壌型 | pH(H2O) | カリウム | カルシウム | マグネシウム | アルミニウム |
| me/100g | me/100g | me/100g | me/100g | |||||
| 美濃市 | ヒノキ人工林 | チャート | BD(d) | 4.5 | 0.35 | 0.88 | 0.20 | 11.28 |
| 美並村 | ヒノキ人工林 | チャート | BD | 3.6 | 0.34 | 0.44 | 0.29 | 9.45 |
| 揖斐川町 | スギヒノキ人工林 | 泥岩 | BD(d) | 4.3 | 0.23 | 0.66 | 0.19 | 6.27 |
| 東白川村 | ヒノキ人工林 | 溶結凝灰岩 | BD(d) | 4.2 | 0.32 | 0.54 | 0.26 | 7.87 |
| 和良村 | スギ人工林 | 溶結凝灰岩 | BE | 4.6 | 0.36 | 2.26 | 0.37 | 3.97 |
| 藤橋村 | スギ人工林 | チャート | BD | 4.4 | 0.35 | 2.54 | 0.53 | 2.98 |
| 関市 | ヒノキ人工林 | 砂岩 | BB | 4.1 | 0.13 | 0.82 | 0.11 | 6.78 |
| 根尾村 | ブナ天然林 | 花崗岩 | dBD | 3.5 | 1.03 | 2.03 | 1.29 | 8.96 |
| 伊自良村 | 針広混交林 | チャート | BB〜Im | 3.8 | 0.25 | 0.09 | 0.06 | 2.09 |
| 瑞浪市 | ヒノキ人工林 | 土岐砂礫層 | rBD(d) | 3.9 | 0.35 | 0.19 | 0.24 | 8.27 |
| 全国平均 | 5.1 | 0.54 | 7.14 | 1.85 | 2.03 |
pH(H2O)は、すべての調査場所で全国平均の5.1より低い強酸性土壌でした。従って、土壌の酸性化に対して緩衝作用のある交換性塩基(カリウム、カルシウム、マグネシウム)も少なく、根尾村のカリウムを除き全国平均より低い値でした。逆に、植物に生長阻害を起こす交換性アルミニウムは、すべての調査場所で、全国平均より高い値でした。美濃市、美並村のヒノキ林は特に高く、和良村、藤橋村のスギ林、伊自良村のスギと広葉樹の混交林は、岐阜県南部の調査場所の中では低い値でした。
根尾村のブナと伊自良村のスギは林分の衰退が認められました。表層土壌のpHが低いことから、土壌の酸性化による影響が予想されます。また、根尾村のブナは樹齢150年、伊自良村のスギは樹齢80年以上であることから、高樹齢による影響も考えられます。
美濃市と美並村の表層土壌は、pHが低く交換性アルミニウムが高いにもかかわらず、成長の良い林分(ヒノキ)でした。これらのヒノキ林では酸性土壌が、現在のところ林分の成長に悪影響を及ぼしていないと考えられます。
今回の岐阜県南部の調査場所を地質別でみてみると、全国レベルでも表層土壌の酸性傾向が認められた酸性火成岩、チャートが大部分を占めていました。今後、別の地質でも表層土壌の酸性化が進んでいるか調査する必要があります。
おわりに
森林に降る雨は、直接降ってくる雨(林外雨)の他に、枝や葉と接触してくる林内雨、樹幹を伝ってくる樹幹流があります。林内雨、樹幹流は、林外雨に樹木からの溶出成分、樹木に付着した降下物等が溶け込み、pHが変化するといわれています。
樹幹流のpHは林外雨のpHと関係なくスギで低く4以下、ブナ、ユリノキで高く6以上と、樹種の違いによる影響が大きいといわれています。また、樹幹流は土壌にも影響を及ぼし、幹近くの表層土壌のpHはスギで低く、ユリノキで高いと報告されています。
現在、当林業センターでも美濃市でユリノキ等の樹幹流を調査しています。今年行った数回の調査では、林外雨のpHが4.2前後であるのに対し、ユリノキの樹幹流のpHは7前後と高い値でした。今後は土壌の化学性を調査して、ユリノキが土壌の酸性化抑制に有効であるか検討していく予定です。