今、マンサクが危ない!
(岐阜県森林科学研究所)大橋章博
岐阜県の林業 2003年3月号掲載
はじめに
マンサクは山で一番早く花を咲かせて、春の訪れを告げる木です。名前の由来も「先ず咲く」からきているといわれています。花のない時期に咲くことや花の形のおもしろさから、茶花にしたり、庭に植えられたりします。マンサクは飛騨地方では“ネソ”と呼ばれ、枝条がしなやかなことから粗朶や薪をしばるのによく使われました。白川村の合掌造りの軸組みは釘を使わずに“ネソ”で縛りあわせるといいます。このようにマンサクは古くから私たちの生活に馴染みの深い植物ですが、最近このマンサクの葉が枯れる被害が各地で発生しており、枯れてなくなってしまうのでは、と心配されています。
そこで今回は、この被害の特徴や原因について紹介します。
 |
被害の特徴
葉枯れ被害は、最初樹冠の一部に発生し、数日で枝全体に拡がっていきます。被害が出始める時期はちょうど5月の連休の頃です。新緑の中で褐変した葉はとても目立ちます。
被害は、はじめに葉柄に近い部分が褐変し、壊死します(写真-1)。この壊死が葉全体に進行し、枯れてしまいます。その後、壊死した部分には黒い小隆起が形成されます(写真-2)。被害葉はやがて落葉しますが、しばらくすると新葉が展開してきます。しかし、その新葉もまた被害を受けて落葉します。こうした被害を繰り返し受けることによって木は衰弱し、数年で枯死します。
 |
被害の分布
被害は1998年に愛知県から初めて発見されました。翌年には岐阜県、静岡県からも被害がみつかっています。その後、各県で調査が行われた結果、被害は本州、四国に広く分布していることがわかりました(図-1)。岐阜県内では広い範囲で被害が発生しています(図-2)。被害が未発生の市町村もその多くは調査不足によるもので、調査が進めばほとんどの地域から被害がみつかると思います。
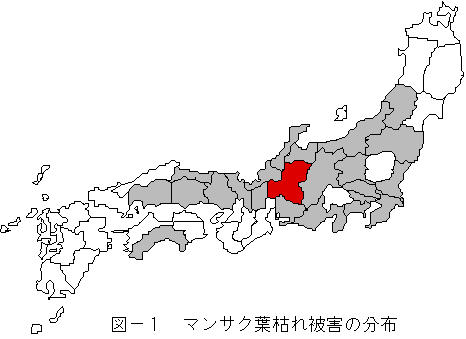 |
被害の原因
被害の特徴から、被害の原因は微生物と考えられます。そこで、被害葉から病原菌の分離を試みました。その結果、Phyllosticta属のかびが高い頻度で分離されました。さらに、Phyllosticta菌が本病害の病原菌であるか否かを判断するため、マンサクの苗木に接種試験を行いました。しかし、今回の試験では病気を再現することは出来ませんでした。とはいえ、これでこの菌が病原菌ではないと決まったわけではありません。今後は菌の接種方法や接種時期を検討して再試験を行うとともに別の菌が病原菌である可能性についても検討していく予定です。
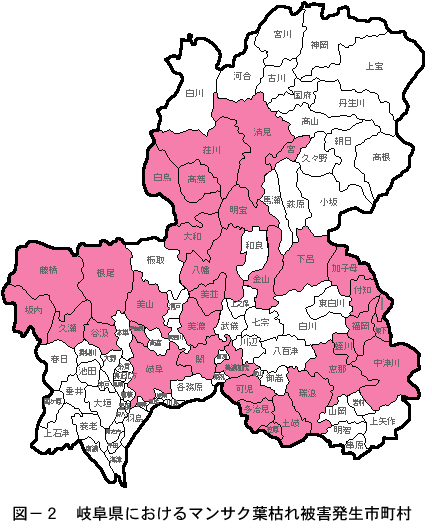 |
おわりに
先にも書いたように、この被害が顕在化したのは1998年のことです。だとすれば、被害がわずか4年で日本各地に拡がったことになります。しかし、病原が「かび」であると仮定すると、その拡がり方はあまりに急激だと思います。それでは、もっと以前から発生していたけれど被害に気付かなかったのでしょうか?それとも細々と発生していた病気が環境の変化をきっかけに大発生したのでしょうか?いろいろな推測はできますが、何の裏付けもないのが現状です。昔から被害があったのか、なかったのか、といった情報をお持ちの方は是非とも教えて下さい。
今後はこうした不明な点を一つずつ明らかにしていき、マンサクが希少種とならないよう研究を進めていきたいと思っています。
このホームページにご意見のある方はこちらまで